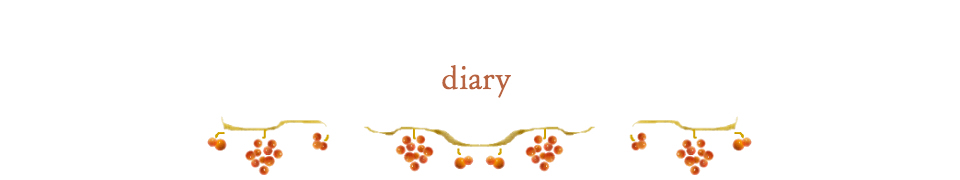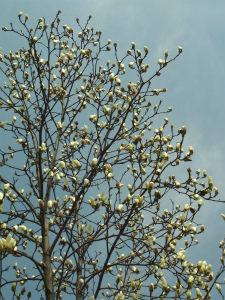「出会ったもの・こと」カテゴリーアーカイブ
けいちつ
先日、とある小さな中華料理やさんに行ったとき、入り口近くで、
「冬眠中」と書かれたダンボール箱を見かけました。
???
いったい何が冬眠しているんだろう?と思って、
勘定を済ませ、店を出るときにダンボール箱の隙間からちょっとのぞいてみると、
どうやら中には水槽があるみたい。
ダンボール箱の隙間はとても小さなもので、
当然のことながら箱にすっかり覆われて中は真っ暗だったので、
水槽の中に何がいるのかまではわかりませんでした。
今日は、家のすぐ近くにあるお寺の
梅の花が咲き始めているのを見かけました。
毎年、通りがかりにふわりとよい香りを届けてくれる梅の花。
あ〜、もうそんな季節か…と思って調べてみると
暦の上では、3月6日頃は「啓蟄」なのだそうです。
冬眠していた虫たちや動物たちが、冬ごもり(蟄)からひらかれる季節。
そういえば、中華料理やさんの「あの子」も
もうそろそろ目を覚ますときが近づいているのを
どこかで感じとっているのかしらと思って、
ふと、このことを思い出したのでした。
次に行ったときには、きっと会える…
かな。

雪の夜
中村えい子さんの作品のこと
哲学の道にあるギャラリー花いろさんで、中村えい子さんの「手織りArt〜おしゃべりな糸たち〜という個展が今日まで開催されているというので、お散歩がてら見に行ってきた。
コットンやシルク、ウールなど様々な種類、太さ、テクスチャの糸で織られた織物。どれも平坦ではなく、織物自体に凸凹とした起伏があったり、ぽこぽこと糸が飛び出しているところがあったり、編み目にも大きなところや小さなところがあったり…。
また、その色も単に「グラデーション」というには収まりきらない、様々な色の糸が複雑に織り込まれているものでとても表情豊かな織物だった。なんだか織物自体が生きて呼吸しているみたいな…。
ご本人もいらっしゃったのでいろいろとお話をうかがった。一番印象的だったのが、作るときには全体の「イメージ」はあるが、具体的にここをこうして…という「計画」のようなものはなく、だから当然下絵なども書かない、ということ。
ただ今日織る部分(小さな織り機の、これから織る部分)で、自分が、いいな〜と思うように、あるいは、ここはこうしてみようと思うままに織っていくのだ、と。そして、そのようにして毎日毎日織っていくと、その結果としてこういう作品ができる、というのだった。
これほどまでに複雑で豊かな世界が、実は全体としてあらかじめ計画されて作られたものではなく、今、目の前にある部分を、自分が「いいなー」と思うように織っていった、その一つの結果として最後になって初めて現れたものなのだ、ということをとても興味深く思った。
自分があらかじめ決めた通りに(すべてを自分でコントロールして)作られた作品ではなく、全体としてどうなるか自分でもわからない、というところを含んでいる。動きのある、そしてどこか呼吸する音が聞こえてきそうな作品…。
織物は経糸と緯糸があって、それらを交錯させて織り上げていく。その中で経糸はあらかじめ決められているもの。それにどう緯糸を入れていくかによって織物に表情が出てくる。
経糸は決められているものだけれど、緯糸の入れ具合や、経糸それ自体を左右にずらしたりして糸の密度を場所によって変えることで、実は経糸だって変化させられるのだ、とおっしゃっていたことが印象的だった。
笛の音
昨日、陽光に誘われて自転車を走らせていると、市役所の前の通りにすごい人。
何かあるのかなと思って見てみると、いろいろな地域の祭りのパレードでした。
徳島の阿波踊り!
わたしは、女性が笠をかぶって舞うこの踊りが大好きです。
手の動きや足の運び、全体のシルエットがなんとも美しい!
ちょっと「波」を思わせるような動きです。
そして、少し腰を落として踊る男踊り。
見ていてなんだかとても楽しい気分になってきます。
♪踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃそんそん♪というけれど、この踊りを見、そしてあの笛と鉦の音を聞いていると、本当に身体がうずうずしてきます。
阿波踊りと言えば思い出すのが、高校生の時に古典を教えてくれていた女性の先生。徳島県出身のその先生は、一度だけわたしたちの前で踊りを見せてくれたことがありました。
しかし、実際に本場の阿波踊りを観に行ったことはまだ一度もなく…。パレードという形ではあるものの、このように連で踊っているのを目にしたのは生まれて初めてだったので感激…でした。一度本場で見てみたいものです…!
通りすがりだったのですべての祭りは見られなかったのですが、
他にこんなのも見せていただきました。
乙部さんさ踊り
軽やかにステップを踏みながらの軽快なバチさばき…

遠州 横須賀三熊野神社の祭礼の際にひきだされる「ねり(山車)」
頭を左右にふるようにして、ゆっくりと前に進んでいました。

パレードという形で、次から次へと出てくるいろいろな地域の祭りを目にしていると、まるで日本全国を瞬間移動で旅しているような感覚になりました。