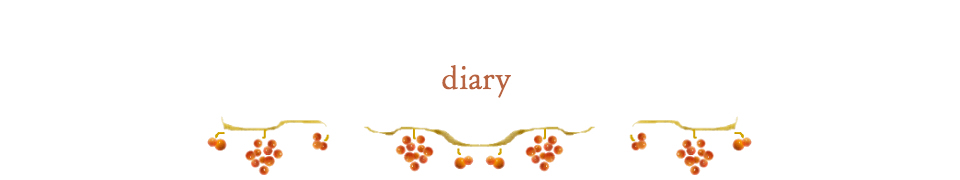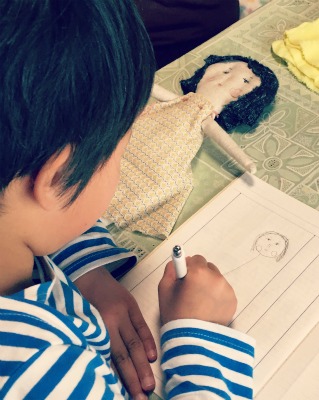先日の新作UPの際には、たくさんの方にご来店いただき、どうもありがとうございました。
お買い上げいただいたお客さま、本当にどうもありがとうございます。
いただいたメッセージ、いつも嬉しく、有り難く、拝見させていただいています。
お客さまからいただくお言葉が、何よりも制作の励みになっていて…
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
秋冬に、ちいさな、ささやかなぬくもりをお届けできるように、また少しづつ制作していきたいと思っています。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
*****
写真は、先日見かけた黄色い曼珠沙華。


祠のそばにひっそりと。
彼岸花、天蓋花、狐花、天涯草、幽霊草、三昧花…。
方言まで入れると千以上の呼び名が、曼珠沙華にはあるそうです。