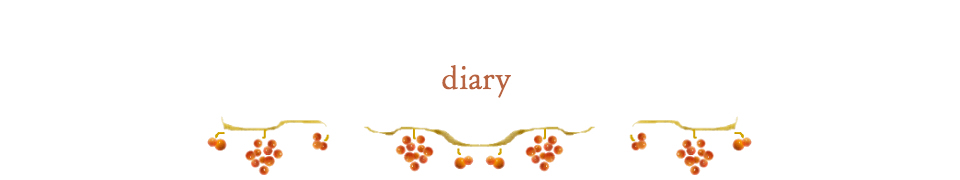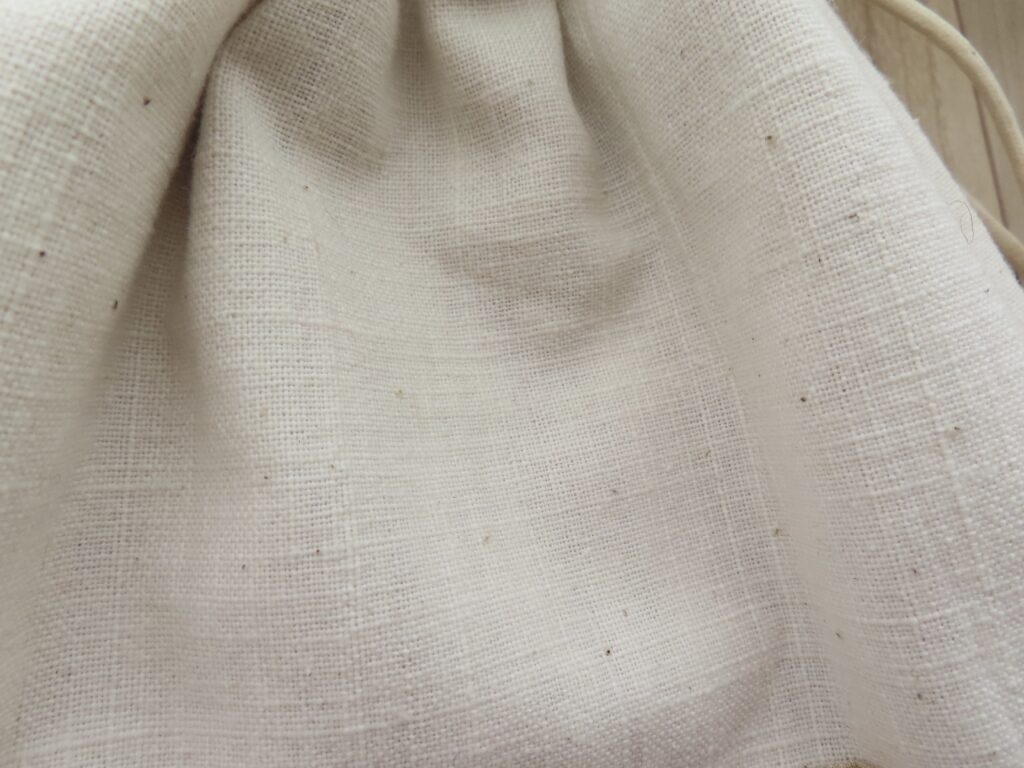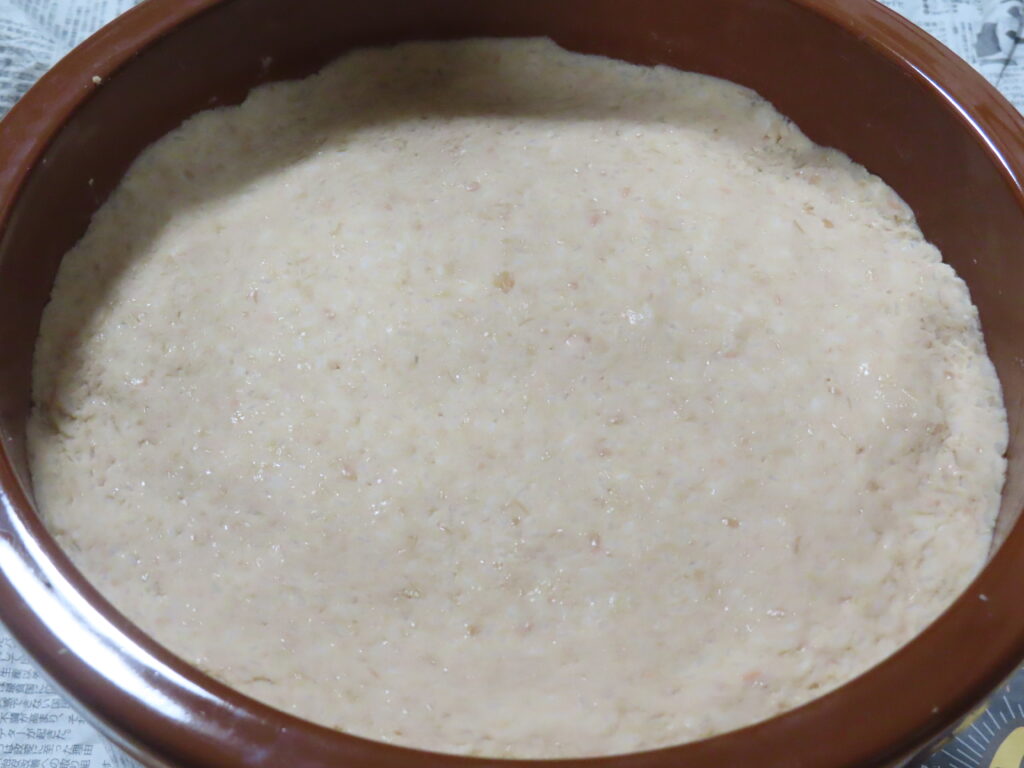あまりに暖かかで梅の花もすっかり咲いているので、例年より少し早いのですが、芽出ししていた種芋を、昨日無事に植え付けました。
植え付けた後、庭を見て回っていると、アゲハ蝶が羽化して羽を乾かしているところに遭遇。

まだいくつか、蛹の状態でいる子がいます。
うちにはレモンの木があって、まだ一度も実が成らないのですが、レモンの葉っぱがアゲハの幼虫のえさになり、毎年そこにたくさん卵が産みつけられるので、たくさんの幼虫と蛹を見かけます。
それでも、自然の中で羽を乾かしているところを見たのは初めてでした。
*
昨年うちにやってきた福寿草は、今年も芽を出してくれました。(写真の真ん中)

あの暑い夏を乗り越えて、いのちをつないでいてくれて、ほんとうにうれしい…
ありがとう、という気持ちでいっぱい。
*
連日の晴天から一転して、今日は久しぶりの雨。
大地に水がゆき渡り、潤って、あたりはすっかり春の気配に満ち満ちています。
急に気温が上がっていたので、ここで雨が降ってくれると、ほっと落ち着いた感じが出て、よいですね。
雨が少なかったので、草木も喜んでいる感じがします。